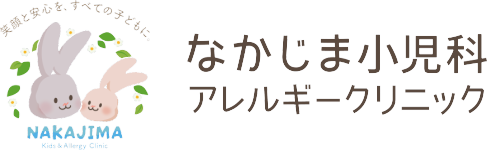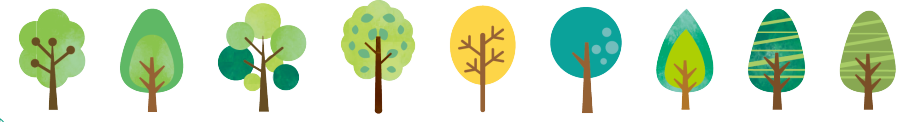
気管支喘息について
こんなことで心配していませんか?

- 風邪をひくとゼーゼーと苦しそうになる
- 医療機関で「喘息っぽい」と言われたが、はっきり診断されていない
- 吸入治療を受けたことはあるが、喘息と確定はされていない
- 喘息と診断されて薬を使っているが、いつまで続ければよいのか不安
- 走ったり運動すると、すぐにしんどくなる
小児の気管支喘息とは
気管支喘息は、お子さんの気道(空気の通り道)に慢性的な炎症が続くことで、発作のときに気道が狭くなり、咳やゼーゼー・ヒューヒューといった呼吸症状を繰り返す病気です。
なぜ喘息になるの?
喘息は「遺伝的な要因」と「環境的な要因」が組み合わさって発症します。
遺伝的要因
- アレルギー体質(アトピー体質)が関係しており、ご家族に喘息や花粉症、アトピー性皮膚炎などのアレルギー疾患を持つ方がいると、発症しやすい傾向があります。
環境的要因・悪化因子
- ダニやハウスダスト:布団やカーペットに潜むダニは代表的な悪化因子です。
- 感染(かぜ):ウイルス感染がきっかけで発作が起きやすくなります。
- たばこの煙(受動喫煙):喘息を悪化させる大きな要因です。
- 花粉や動物の毛:アレルギーを持つお子さんでは悪化因子になります。
- 天候や気温の変化:季節の変わり目や寒暖差でも発作が出やすくなります。
- 運動:激しい運動の後に症状が出ることがありますが、治療をしっかり行えば多くのお子さんは運動可能です。
診断と検査
喘息の診断は、症状の特徴や経過を丁寧に確認したうえで、必要に応じて検査を行い総合的に判断します。
症状の特徴
- 夜間・早朝に咳が続く
- ゼーゼー、ヒューヒューという呼吸音
- かぜの後に咳が長引く
- 運動で咳や息苦しさが出る
検査の方法
- 呼吸機能検査(スパイロメトリー):学童期以降に実施可能です。息を吐き出す速さや量を測ることで、気道がどのくらい狭くなっているかを客観的に評価できます。気管支拡張薬を使ったあとに再度測定することで、薬でどのくらい改善するかも確認できます。
- 呼気NO(一酸化窒素)測定:吐いた息に含まれるNOの量を測定し、炎症の程度を知ることができます。
- 血液検査:アレルギー体質(IgE、好酸球など)の確認に用います。
- 胸部X線検査:喘息以外の病気を除外する目的で行うことがあります。
- 乳幼児の場合:検査が難しいため、症状の経過や治療への反応を重視して診断します。
治療の方針
喘息治療は「発作への対応」と「長期的な管理」の両輪で行います。
- 発作時治療(リリーバー)
発作が起きたときに使う薬です。気管支を広げて呼吸を楽にします。
- 短時間作用型β2刺激薬(SABA)の吸入薬
- 症状が強い場合にはステロイド内服や点滴が必要になることもあります。
- 長期管理(コントローラー治療)
発作を繰り返さないように炎症を抑える薬を毎日使います。
- 吸入ステロイド薬(ICS):治療の中心。気道の炎症をしっかり抑えます。
- ロイコトリエン受容体拮抗薬(LTRA):小児でも使いやすい内服薬で、アレルギー性鼻炎にも有効です。
- 長時間作用型β2刺激薬(LABA):ICSと併用し、症状がコントロールしにくい場合に使用します。
- 抗IgE抗体(オマリズマブ)などの生物学的製剤:重症喘息に対して使用されます。
ガイドラインでは「ステップ治療」という考え方に基づき、症状の重さに応じて薬の種類や組み合わせを調整します。2〜3か月を一つの期間として、薬の量を増減していきます。
治療の目標
- 発作を起こさず、夜も安眠できる
- 学校や運動に制限なく参加できる
- 救急外来や入院を必要としない
- 薬の副作用を最小限に抑える
まとめ
喘息治療薬は以前に比べて大きく改善し、適切に治療を行えば症状なく生活できる病気になっています。
喘息でも、オリンピック選手やプロスポーツ選手はたくさんおられます。
正しく診断し、最新のガイドラインに基づいて管理することで、お子さんは安心して学校や運動に取り組むことができます。
当院では、お子さんの症状や生活スタイルに応じて最適な治療を提案し、ご家庭と一緒に歩みながら長期的にサポートいたします。喘息があっても、健やかな成長を妨げないように一緒に見守っていきましょう。